|
リヨンオペラ座の子供向けの出し物として僕がアンサンブル・アゴラの為に編曲した「アルルの女」がこの3月に取り上げられました。この編曲は勿論演奏会でそのまま演奏してもよいようになっているのですが、先年CDつきの絵本として出版され、今回はその挿絵(エリーズM)を投影しながら舞台俳優のピエール・デスマレがドーデのテキストを読みながら進めていくといった趣向で行われました。
「アルルの女」はアルフォンス・ドーデの「風車小屋便り」の中の物語のひとつですが、格調高い名文中にプロヴァンスの風物がちりばめられた美しくも悲しい物語です。
以下 物語を簡単に要約します。
《ジャンはプロヴァンスの村に住む二十歳、明るい性格と美しい容貌から誰にも愛される好青年です。村の多くの若い女たちもジャンに関心を寄せています。しかしジャンの心中には或る時偶然に知り合ったアルルから来たという乙女しかありません。ところが、このアルルの女の素性を知るものは村のどこにもいません。『一緒になれないなら死ぬしかない』ジャンは訝る両親を必死に説得して許嫁にする約束をさせます。日曜日の夜婚約の祝いを兼ねた夕食が開かれました。彼女はどうしたことか現れませんが、家族一同彼女のためにおおいに飲みました。
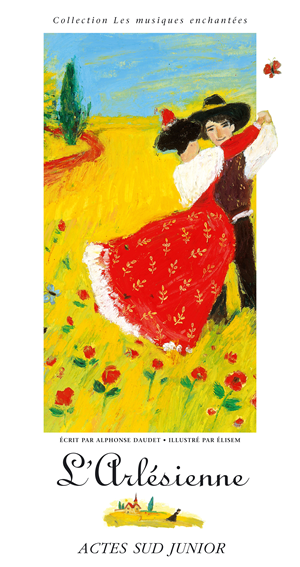 夜遅くなってからその席にある見知らぬ男が尋ねてきます。男は、あのアルルの女を2年間囲っていた者だが、ジャンが現れてからこのかた私に近づこうとしなくなった、と父親に告げます。それを知ってからジャンは、ある日は庭の片隅に座ったまま日長一日何もせず過ごしたかと思えば、ある日は十日分の野良仕事を気が狂ったように一日で片付けてしまったり、という日々を送ります。ジャンの心には今もアルルの女以外にありません。心配のあまり母親はジャンに、それほどの事なら恥を忍んででも結婚を承諾しても良いとまで言いますが、ジャンは静かに首を横に振るのみ、立ち去ってしまいます。 夜遅くなってからその席にある見知らぬ男が尋ねてきます。男は、あのアルルの女を2年間囲っていた者だが、ジャンが現れてからこのかた私に近づこうとしなくなった、と父親に告げます。それを知ってからジャンは、ある日は庭の片隅に座ったまま日長一日何もせず過ごしたかと思えば、ある日は十日分の野良仕事を気が狂ったように一日で片付けてしまったり、という日々を送ります。ジャンの心には今もアルルの女以外にありません。心配のあまり母親はジャンに、それほどの事なら恥を忍んででも結婚を承諾しても良いとまで言いますが、ジャンは静かに首を横に振るのみ、立ち去ってしまいます。
その日を境に、ジャンは夜には街の酒場に顔を出したり、村の集まりには率先してファランドールを踊ったり、すっかりもとの明るい性格に戻ります。父親はジャンがすっかり恢復したと安心しますが、母親だけはその明るさに一抹の不安を覚えます。
村祭りの日がやってきて、家族総出で祭りを楽しみました。母親もジャンの誘いでファランドールを踊り、楽しさのあまり涙まで流します。夜になりジャンもいつものように弟とベッドを並べて床に就きます。その明け方近く母親は物音で目覚め部屋を出ると、階段を駆け上り屋根裏部屋に向かうジャンの姿が目に入りました。呼び止めても振向きもせずジャンは階段を駆け上り屋根裏部屋に入り、その後は窓を開ける音に続いて身体が中庭の石畳の上に叩き付けられる音が耳に入るだけでした。朝露と血に染まった中庭の石畳の上で母に抱かれて、ジャンは息を引き取りました。》
「アルルの女」は現在ではフルオーケストラ版の第一、第二組曲のみで有名ですが、原曲はドーデの原作に基づく戯曲の劇音楽として1872年に作曲されました。この時のオーケストラの編成が変わっていて、第一ヴァイオリン 4、第二ヴァイオリン 3、ヴィオラ 1、チェロ 5、コントラバス 2、フルート 2、オーボエ(イングリッシュホルン)1、 クラリネット 1、バスーン 1、ホルン 2、サクソフォン、ピアノ、ティンパニ、プロヴァンス太鼓、といった計26人編成のものでした。サクソフォンを初めて積極的にオーケストラに取り入れた曲として歴史的にも価値がある曲です。この編成は、おそらくビゼーが積極的に選んだのではなく上演当時の劇場のピットの大きさとかそのときに雇えたミュージシャンの都合などで決まったのでしょうが、その制約を乗り越えてむしろこの編成が必然であったような、見事なオーケストレーションとして仕上がっています。(因みにこの原典版はリヨンオペラ座管と J,E、ガーディナーで1987年に録音されエラートから出ています。まだ出回っているかどうかは解りませんが)
ワーグナーやR,シュトラウスの頃から大編成のオーケストラが一般的になってきて、こういった編成は変則的なものと受け止められがちですが、現実的には大きなオペラ座や組織された大編成のオーケストラの委嘱作品で無い限り現在でも、というか現在は尚の事、フルオーケストラの為の作曲は稀なのが現実です。
そもそも作曲という作業は、楽器(又は声)の機能的制約や、演奏するロケーションの空間的制約が必ず付きまとい、それを如何にクリアーしながら自己のイデーを表現してゆくかが作曲家にとっていつも問題になるものです。優れた作曲家はこうして与えられた《不自由》の中をかいくぐって自己の精神を解き放つ自由さを見つけた時ほど優れた作品を書くのではないでしょうか。「アルルの女」はそういった意味でも優れた作品です。 例えば、前奏曲の後半に現れるサクソフォンのテーマは、劇音楽の中にも弦楽四重奏で現れますが、無限旋律的なこのテーマは旋律の美しさ、和声の巧みさが聞く者の心を強く惹きつけます。このテーマの後ろでクラリネットが単調なテーマを複雑な転調にもかかわらず文字どおりオスチナート(執拗に)で繰り返すところは、和声的にもかなり大胆で、心を引裂くような音楽を作り上げています。劇場的には当然何かを物語っているのでしょうが、そもそもこの戯曲の台本は紛失したまま現在に至っているので、どういった場面でどの音楽が使われたのかは残念ながら想像の範囲を超えません。ジャンの放心のような気もしますが?
もうひとつ有名な名曲としてアダージェットがあります。この曲も現在ではフルオーケストラの弦楽セクションで演奏されることが一般的ですが、原曲は弦楽四重奏に書かれています。僕は何度かこれをカルテットのアンコールで取り上げて演奏しましたが、こっちの方が音楽が引締りより強く表現的に聞こえるように思われます。マーラーのアダージェット風に過剰なセンチメンタリズムに陥りがちな弦楽アンサンブル版に比して、原典版はベートーヴェンやシューベルトの弦楽四重奏曲により近い精神性を感じます。
戯曲の不成功をよそにビゼーは、前奏曲、メヌエット(あの有名なフルートとハープのそれではなくもう1曲の方)、アダージェット、カリヨンの4曲をコンサート用フルオーケストラに書き直し成功を博します。この書き直しは時代的な通例としてこういった編成にせざるを得なかった部分があるのではないかと思います。この書き直しによって得た名声の代わりに、この音楽の持っている本質的な凄さも、どこかで失われたような気がしてなりません。
ビゼーはこの3年後の1875年にわずか36歳でこの世を去ります。第一組曲の成功に気を良くした出版社シューダンは、ビゼーの友人でカルメンのレシタティーヴォを書いた、エルネスト・ギローに第二組曲の編曲を依頼します。ギローは「パースの美しい乙女」というビゼーの別のオペラからメヌエットを挿入し(これが前述のメヌエット)、さらにファランドールはビゼー本人のアイデアだったこともあり大幅に拡大して、「王の行進」(前奏曲の冒頭のあの有名なテーマ、プロヴァンス民謡)ともうひとつのプロヴァンス民謡であるファランドールを重ねて、コンサート用のフィナーレとして華やかな曲に仕上げます。しかしこの劇音楽全体が持っている悲劇性はこれと同時に失われてしまいました。ギローのオーケストレーションもビゼーのそれに僅かに劣るとはいえ第一級のもので、こうして組曲だけが一人歩きするようになったのも頷けないわけでは無いのですが。
追記 ピエール・デスマレ氏に先日聞いたところパリの国立図書館にアルルの女の劇場用台本が保存されているそうです。
|
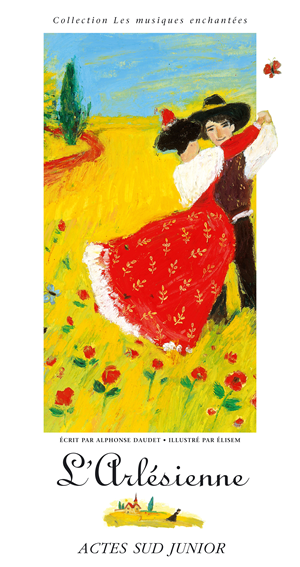 夜遅くなってからその席にある見知らぬ男が尋ねてきます。男は、あのアルルの女を2年間囲っていた者だが、ジャンが現れてからこのかた私に近づこうとしなくなった、と父親に告げます。それを知ってからジャンは、ある日は庭の片隅に座ったまま日長一日何もせず過ごしたかと思えば、ある日は十日分の野良仕事を気が狂ったように一日で片付けてしまったり、という日々を送ります。ジャンの心には今もアルルの女以外にありません。心配のあまり母親はジャンに、それほどの事なら恥を忍んででも結婚を承諾しても良いとまで言いますが、ジャンは静かに首を横に振るのみ、立ち去ってしまいます。
夜遅くなってからその席にある見知らぬ男が尋ねてきます。男は、あのアルルの女を2年間囲っていた者だが、ジャンが現れてからこのかた私に近づこうとしなくなった、と父親に告げます。それを知ってからジャンは、ある日は庭の片隅に座ったまま日長一日何もせず過ごしたかと思えば、ある日は十日分の野良仕事を気が狂ったように一日で片付けてしまったり、という日々を送ります。ジャンの心には今もアルルの女以外にありません。心配のあまり母親はジャンに、それほどの事なら恥を忍んででも結婚を承諾しても良いとまで言いますが、ジャンは静かに首を横に振るのみ、立ち去ってしまいます。